新年度が始まり、子どもたちは新しい環境や友達、先生との関係に少しずつ慣れ始める時期。ところが5月に入ると、「学校に行きたくない」「元気が出ない」といった声が聞かれることも。
これがいわゆる 「5月病」 と呼ばれる状態です。
大人だけの問題と思われがちですが、実は子どもも同じように心や体に負担を感じています。今回は、子どもの5月病に気づくサインと、やさしく寄り添うための対処法を紹介します。
子どもの5月病とは?
5月病は、新しい生活の疲れやストレスが心や体に現れる状態。子どもの場合、こんなサインが見られることがあります。
朝起きられない、学校に行きたがらない
食欲不振、眠れない
イライラする、泣きやすい
頭痛やお腹の痛みが続く
元気がなく、好きだったことに興味を示さない
どれも一見些細な変化に見えますが、子どもなりの「SOS」かもしれません。
親ができる5つの対処法
1. まずは「話を聞く」ことから
子どもの気持ちを否定せず、ただ「聞く」姿勢を大切に。「そう感じたんだね」「つらかったね」と共感するだけで、子どもは安心します。
2. 生活リズムを整える
夜更かしや休日のダラダラを避け、早寝・早起きを心がけましょう。睡眠と食事は、心と体の回復に不可欠です。
3. 無理に登校させない
無理して学校に行かせようとせず、休む選択も大切です。子どものエネルギーが回復するまで、ゆっくり見守ってあげましょう。
4. ポジティブな言葉で安心感を
「今日もよく頑張ったね」「ここまでできたのすごいよ」と、できたことを具体的に褒めましょう。自信と安心につながります。
5. 学校や専門家に相談する
症状が長引く場合は、担任の先生やスクールカウンセラーに相談を。専門機関や小児精神科にかかることも視野に入れておきましょう。
参考にしたい記事・サイト
子育て中の保護者におすすめの、信頼できる参考ページを紹介します。
子どもの五月病を考えよう!気をつけないと不登校にも!|TKKアカデミー
寄り添うことが大切!子どもの「5月病」|たまちっぷす

GW明け子どもがぐずる!保育士ママが伝授する5月病のサインと対処法|Enfant

まとめ
子どもの5月病は、心と体が「ちょっと休みたい」と伝えているサイン。大人がその声に気づいて、無理をさせずに寄り添ってあげることが何より大切です。
「学校に行けないこと」が悪いわけではありません。安心できる家庭の中で、少しずつ元気を取り戻していけるようにサポートしていきましょう。


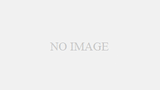

コメント