『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』は、産業カウンセラーの神田裕子氏による実用書で、職場の人間関係の悩みを6タイプに分類し、それぞれへの対処法を心理学的に解説しています。
ただし、「困った人」という表現や障害と結びつけた分類が差別的と批判され、話題になっています。発売は2025年4月24日予定です。
なぜ批判されているのか?
一番の問題点とされているのは、「困った人」の分類方法です。本書では、職場で関わりにくい人を6タイプに分けて紹介しており、その中には発達障害(ASD・ADHD)や愛着障害、トラウマ障害など、医療や福祉の領域で扱われる状態が含まれています。
これに対し、多くの当事者や支援者からは「困ったのは本人じゃなくて周囲の対応のほうでは?」という声や、「障害を持つ人を“職場の問題児”として扱うのは差別的」といった批判が寄せられています。
表現方法にも疑問の声
さらに火に油を注いでいるのが、本文に登場するイラスト。たとえば、ADHDタイプの人を「ひらめきダッシュさん」などとキャラクター化し、動物のように描いたビジュアルに対して、「茶化しているようで不快」「ステレオタイプを助長する」と感じる読者も多くいます。
当事者団体も反応
発達障害当事者協会は、出版社に対して正式な質問状を提出し、表現の見直しや今後の対応について説明を求めています。このように、出版の倫理や当事者の尊厳を守ることの重要性が、改めて問われている状況です。
—
まとめ:どう読むかは読者次第
この本のテーマ自体は、「人間関係の悩みをどう乗り越えるか」という問題に切り込むもの。ただし、それをどんな視点で、どう伝えるかは非常に繊細な問題です。
なぜこうした批判が生まれているのか、自分自身の関わり方と照らし合わせて考えることが大切かもしれません。


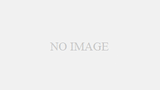
コメント